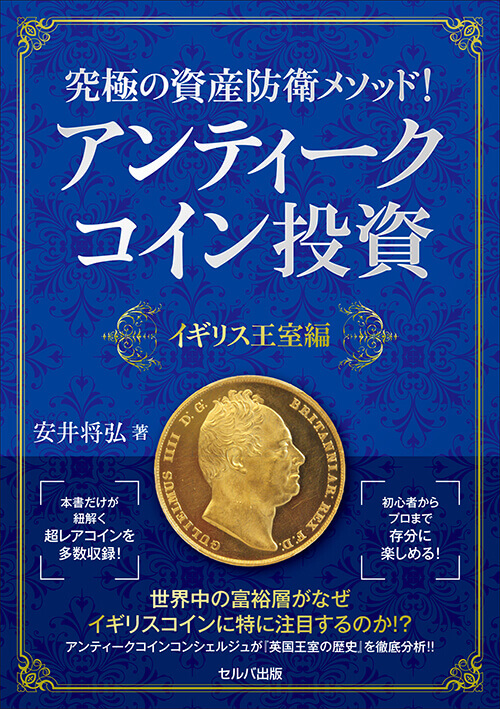皆様こんにちは、コインパレスの室田でございます。如何お過ごしでしょうか?
おかげさまで、今回で私の英国に関するエッセイは第三弾を迎えます。
今回のエッセイは新緑の季節、六月のイングランドにスポットを当て、百花繚乱の薔薇の数々を摘み取りブーケにして、六月のイングランドののどかな風景と共に日本の読者の皆様にお届けしたいと思います。
パリからユーロスターで大英帝国の首都ロンドンへ到着

久しぶりの訪問であった花の都パリでのごく短い滞在のあと、高速列車ユーロスターに飛び乗り2時間15分、最終目的地である大英帝国の首都ロンドンの表玄関セントパンクラス・インターナショナル駅のプラットフォームへの到着は定刻通りで、ほんの少しずつ旅の始まりの実感が湧いて来るようでした。
今日はこのロンドンの中心で、明日の準備のため大忙しの一日になることはほぼ間違いないでしょう。宿泊先のストランド街にある老舗のサヴォイ・ホテルへのチェックインを早々と済ませ、同ホテルのグランドフロアーにある優美の極致と言っても過言ではない「テムズ・フォワイエ・ティールーム」のあらかじめ予約しておいたテムズ川よりの席で、ため息が出るほど濃厚な色彩感を見せるアールグレイ紅茶とともに、ホテルのオリジナルレシピ―による秘伝のデザート「ピーチ・メルバ」を心ゆくまで堪能することにします。
このデザートは今から約100年前、サヴォイに常宿していた世紀のオペラ歌手、デイム・ネリー・メルバ(1861-1931)のために、往年の名料理人でフランス人のジョルジュ・オーギュスト・エスコフィエ(1846-1935)が考案したとされる、飴細工が施された冷たい桃の華麗なるデザートで、旅の始まりのひとときに彩を与えてくれるその高度な職人技には目を見張るものがあります。
ティールームの窓から悠久のテムズ川の流れを眼下に見下ろし、明日目前に繰り広げられるはずの6月のイングランドならではの数々のドラマティックな光景を胸に思い描き、ソファーに身を埋めて数時間寛ぐことにします。午後のイングランドの心地よい静謐感漂うティータイムは、天空を駆け巡るハープの音色を伴って延々と優雅に続くのでした。
華麗なるシーズンの幕開け・300年目のロイヤル・アスコット競馬
昨日の真夜中から降り始めた雨は今やほとんど土砂降りに近く、きょうの午後最終日を迎える英国王室主催のロイヤル・アスコット競馬の開催が危ぶまれるほどその雨は激烈極まりないものでした。
朝になっても止む兆しは頑として見られず、何度も鉛色の大空を見上げてはイングランドの気まぐれな気候にただただ嘆息するほかありませんでした。
その後雨足の弱まりを感じ、窓を開けて外を見渡しますと、雲の合間から広がりのある優しい光が差し込み、テムズ川とその辺り一帯の景色にあまねく降り注ぎ始めていました。
この時ぞとばかりに支度を終え、30分後にはアスコット行の列車が発着するロンドン・ウォータールー駅のプラットフォームに帽子と共に佇んでいました。
着飾った紳士淑女たちで超満員のアスコット行の列車に揺られ、中間地点のレディングを経由し、ついに風光明媚なアスコットに無事到着します。
雨上がりのひんやりとした競馬場までの道中は清々しく、帽子姿の貴顕たちの列がどこまでも続く壮観を目の当たりにすることはアスコットならではの楽しみの一つです。
アン女王の治世に創始された国際的な競馬のイベントであるロイヤル・アスコットは今年で300周年を迎えますが、現在に至るまでイギリス上流階級の社交場としての機能を十全に果たし、また例年エリザベス女王をはじめとする英国王室のメンバーが全員揃うことから「ロイヤル・ミーティング」もしくは単に「ミーティング」と親しみを込めて呼ばれ、イングランドの初夏の風物詩として今日まで数々の伝説と共に語り継がれています。
土壇場で奇跡的に開催される運びとなった本日が最終日のロイヤル・アスコットですが、午後2時には主催者であるエリザベス女王の来臨が告げられ、かつての伝統と格式の大英帝国の偉容と神秘が、国歌「神よ女王を守り給え」の厳粛な旋律とともに、帽子の花が咲き乱れる場内についに姿を現しクライマックスを迎えます。
女王の戴冠50周年を記念して創設された「ゴールデン・ジュビリー・ステークス」をはじめ、数々の賞を巡ってその勝敗を二分し、時の経つのも忘れてスリルとスピードに熱狂する着飾った紳士淑女で埋め尽くされた観客席は、実際に競馬が行われるレースコース以上に壮観で、英国ならではの階級社会のまた別の一面を垣間見る思いがします。
本日の賭けの方は致命的で、馬券購入のために費やした500ポンドは一瞬にして海の藻屑と消え、ロイヤル・アスコット300周年での勝利を祝してのとっておきのワイン購入計画は叶わぬ夢に終わります。
アスコットで体験すべき全てのドラマをあらゆる角度から見届け、たそがれ時の競馬場の黄金色の輝きを後にするとき、午後の到着時にはなかったずっと穏やかな幸福感でゆっくりと心が満たされていくのを感じ、こみ上げてくるイングランドに対する敬愛の気持ちを胸に帰路を急ぐのでした。
そこはこの世の天国
グラインドボーン・オペラフェスティバル
世界には無数の優れたオペラハウスやオペラフェスティバルが存在しますが、ここ南イングランドのグラインドボーン・オペラフェスティバルは別格で、最も英国的かつ貴族的な6月のイヴェントとして、世界中にその名を轟かせています。ロンドン・ヴィクトリア駅から港町ブライトン行き列車に乗り、約1時間で最寄り駅ルイスに到着します。
ルイスからグラインドボーンまでは専用バスで約30分の道程で、晴れた日にはこの世の天国と呼んでも差し支えない南イングランドの絵画的な田園風景を目の当たりにすることになります。
1934年に英国貴族の末裔であるサー・ジョン・クリスティーが自身の荘園付き邸宅にオペラハウスを建立したことがこのフェスティバルの発端で、彼の没後クリスティー家によって代々運営されて今日に至ります。
到着後赤レンガ造りのゲートを潜り抜け、敷地内に足を踏み入れるとイブニングスタイルのゲストたちがシャンパングラスを片手にくつろいでいる様子が目に入ります。細い通路を通って裏庭に出てみますと、そこにはイングランドの理想を描いたような見事な大パノラマが180度に渡って眼前に広がり、延々と続く緑の絨毯には無数の羊がのんびりと寛いで時の移ろうがままにその景色と溶け合っていました。
スコットランド産とみられるタータンチェック柄のウールの絨毯を芝生の上に敷いて、オペラが始まるまでの午後のひと時を、チーズやキャビアと共にシャンパングラスを傾け、気の合う仲間と心行くまで楽しむドレスアップしたゲスト達で溢れかえるグラインドボーンほど、今日まで田舎での生活に重きを置き、人生の基盤として着実に生きてきた英国人の真の郷土愛を感じさせる場所は他に無いように思われます。
この通称「グラインドボーン・ピクニック」と呼ばれる習慣は、オペラの上演から離れて長く愛され続け、今後も英国がこの世に存在する限り永久に存続することは間違いないと言われています。
今回はカール・マリア・フォン・ウェーバーの珍品オペラ「オイリアンテ」を観ることが目的でしたが、そのロマン派の純粋な音楽は、現代木造建築の粋ともいえるグラインドボーン・オペラハウスの隅々にまで響き渡り、その素朴で健康的な温かみのある劇場空間を満たし、時間を超越する成熟した美しさがここで育まれ発信されているということを体感する結果となりました。
貴族の荘園を有する天下の絶景と極上のオペラの両方を人里離れたこのグラインドボーンで体験するということは、イギリス式の「人生とは何か」に対する最良の答えになっているように感じます。
天才レオナルド・ダヴィンチ畢生の傑作:ロンドンの「岩窟の聖母」

今回のイングランド旅行も残すところあと6時間となりましたが、最終日の今日までにやっていなかったことを急に思い出し、トラファルガースクエアに急ぎました。ロンドンが誇るナショナルギャラリーは古今東西の美術品、特に西洋絵画のコレクションの充実では右に出るもののない英国屈指の、また世界最高の美術館の一つです。
コレクションに含まれている絵画はどれも名作ばかりですが、ルネッサンス期の万能の才人レオナルド・ダ・ヴィンチの「岩窟の聖母」は同館屈指の傑作中の傑作で、パリのルーブル美術館所蔵の同じ主題による作品と比べてより高い次元での完成度を誇っており、暗い色彩で描かれた作品の人物描写は鑑賞者の心を捉えて離さない強い呪縛力を伴っています。
中央に描かれた岩窟に身を置く聖母の放心したようなかすかな微笑みとともに、今回のイングランドでの世にも美しい6月が私の心の中で急激に終焉を迎えようとしていました。作品から少しずつ離れ、展示室を出る前にもう一度ダ・ヴィンチの作品のほうを振り向いてみると、額縁の中のマドンナは相変わらず崇高な微笑みを湛えて、もうすぐ愛すべきイングランドを去らなければならない不幸な私を安らかに、そしてしっかりと見届けていました。